秋田県大館市にある「秋田三鶏記念館」の紹介記事です。
また国の天然記念物に指定されている「比内鶏」と「声良鶏」、県の天然記念物に指定されている「金八(キンパ)鶏」の魅力を紹介していきます。
ではどうぞ。
|
|
「秋田三鶏記念館」とは?
秋田三鶏とは秋田県北部で昔から飼育されてきた比内鶏、声良鶏、金八鶏のことです。
- 比内鶏、声良鶏・・・国の天然記念物に指定
- 金八鶏・・・・・・・県の天然記念物に指定
「秋田三鶏記念館」では比内鶏、声良鶏、金八鶏が飼育されていて、ケージ越しに見ることができます。
2010年に秋田三鶏の原種や資料を保存し続けるために建設されました。

秋田三鶏記念館
大館市郷土博物館の敷地内に建設されていて、外観は純和風のデザインとなっています。
秋田三鶏の歴史はとても古く、大館地方を中心に人々に飼育されてきました。
戦争中は食糧難や経済の混乱が起こり、秋田三鶏は産卵できる個数が他の鶏よりも少ないことなどの理由から一時は絶滅の危機におちいりました。
しかし、山田定次さん、横山助成さんを始め「日本の鶏を保護しよう」という声が上がりました。
日本の鶏を保護しようという活動は次第に広がっていき、保護運動が大きくなっていきます。
戦後は当時の大館町長や山田定次さんたち大館地方を中心にして秋田三鶏を保護する活動が活発になったことで今日まで守り抜かれてきました。
なかでも山田定次さんは人生をかけて秋田三鶏の研究と保存に情熱を注いだ人でした。
この人がいなければ今の秋田三鶏はなかったと考えられています。
山田定次さんについて知りたい方はこちらをご覧ください。


秋田三鶏記念館の前に建てられている看板です。
この看板にもまた山田定次さんを讃える言葉が載っています。
鶏博士と言われた山田定次氏は私財を投げうって戦時中の食糧難を乗り越え
秋田三鶏を守り抜いた功績は大いなるものがある
秋田三鶏記念館の館内の紹介
飼育舎では比内鶏、声良鶏、金八鶏がツガイでそれぞれ飼育されています。
比内鶏
比内鶏は昭和17年(1942年)7月に国の天然記念物に指定されました。

比内鶏の性格はとても勇ましいです。
見るからに鋭い目つきをしています。
とさかは茶色で三枚冠、尾っぽの羽根が豊かですね、上写真もふさふさしていますね。
また脚が長いことも特徴にあげられます。
このような容姿になったのは、山あいの農村で放し飼いの状態で飼われていたからだと考えられています。
なかでも大館市の比内地方を中心に生息していた地鶏であったので「比内鶏」と名付けられました。
山にいる野生のキジに似ているとも言われています。
また、当時まだ食用にされていたころはとても美味しいという定評がありました。
これも比内地域の土壌や水と深く関係していると考えられています。
土壌や水にともない生息する雑草や昆虫を食べる比内鶏、比内地方が持つ自然環境と比内鶏の美味しさは間違いなくつながっていると考えられています。
美味しいという評判から、旧藩時代は藩主に年貢として納められていました。
そういった意味で今上天皇、秩父宮、三笠宮に上納した という記録も残されています。
ただし、今現在の比内鶏は国の天然記念物に指定されているので、現在は食用として出荷されていません。
厳密に言うと、
- 野生の比内鶏は食べられない
- 飼育されている比内鶏は食べられる
という区別がありますが、飼育されている比内鶏でも食用にしたという話は聞いたことがありません。
市場に出荷されているものは「比内地鶏」という鶏で、比内鶏のオスとロードアイランドレッドのメスを交配させて生まれた鶏です。
「比内地鶏」もまた高く評価されており、日本三大美味鶏、または日本三大地鶏と呼ばれています。
声良鶏
昭和12年(1937年)12月に国の天然記念物に指定されました。

日本三大長鳴き鶏と呼ばれています。
鳴き方は、はじめは渋く落ち着いた声から始まります。
長く伸ばしながら次第に声を張り上げ、音程を下げつつ最後に止めの一声をかなでます。
15秒ほどの長さが普通ですが、20秒以上も鳴き続ける鶏もいます。
歌声は低音で豪壮、優雅、「ゴッゴ、ゴオー」と緩やかな山を描くような歌声に魅了されられます。
今から約250年前(江戸時代)、大館市を中心とした米代川の辺りで比内鶏と交配させて生まれ、秋田、青森、岩手など主に北東北で飼育されてきました。
体重は5㎏ほどもあり、日本の鶏としては大型で均整のとれた美しい体型です。
太いくちばし、大きく鋭い眼、発達してふくれあがっている喉もとが特徴的です。
羽色は黒、白、まれに黄色も見られます。
また寒さに弱いという特徴もあります。
たしかに見学しに行くといつも奥の方の鶏舎にいるかも。
他に日本三大長鳴き鶏と呼ばれている鶏は、高知県の東天紅鶏、新潟県の唐丸です。
金八鶏(きんぱどり)
昭和34年(1959年)1月の秋田県の天然記念物に指定されました。

比内鶏と声良鶏に比べると小柄です。
今から約150年前(江戸時代後期)、大館町川原町の魚屋金八氏(さかなやきんぱ)によって作られた鶏種だとのこと。
闘争性に優れ、ケンカっぱやい性格の持ち主です。
目つきが鋭いですね。
魚屋金八さん、なぜこのような鶏を作出したかというと・・・・
自分の飼っているシャモ鶏が、となりの家で飼ってる比内鶏とケンカをして負けるからだそう。
隣人の比内鶏が金八さんの庭に飛んできては自分のシャモ鶏とケンカして負ける。
悔しい金八さん、闘争性に優れ、気が強い鶏を作ろうと思ったそうです。
金八さん本人も短気者の金八氏と呼ばれるほどの気性の持ち主で、商売のことよりも鶏に熱中していた人だったそうです。
そんな訳で短気者の金八氏にあやかり、「金八鶏(きんぱどり)」と名付けられたそうです。
金八鶏は大正中期まで大館下町の職人に飼い親しまれていましたが、次第に飼う人が減少していきます。
昭和初期になるとわずか十数羽あまりとなってしまいました。
昭和4年、東京で開かれた共進会に出したキンパ鶏がみごとに一等賞を獲得しました。
学術的にも貴重な鶏であると学者たちが大館に来て現地調査されましたが、あまりにも現存の数が少なかったため、その後忘れ去られてしまいました。
しかし、わずかながらも日本の鶏の保存に対して熱心な人たちが飼育し、守り続けてきた努力によって、秋田県の天然記念物に指定されることとなりました。

絶滅寸前で保護指定されたんですね
年間の産卵数は60個ほどです。
その中から生まれるヒヨコはまれで飼育管理が難しいとされています。
黒い羽色で羽先が丸く、特に尾羽がエビ尾になっているのが特徴的です。
同系のシャモと比べると体が小さいわりに頭は大きく眼光も鋭い。
立姿勢になると頭から脚が垂直になっていることも特徴の一つです。

ところで金八鶏の生み親であった魚屋の金八氏、、、
晩年はヌマのクボ神社の堂守りとなり、金八鶏を飼い続けながら一人ひっそりと余生を送ったと言われています。
記念館の館内
比内鶏を始め、国に指定されている鶏についての資料が展示されています。
一番の見どころはタマゴからかえったヒナです。
4月から6月にかけて行われる作業で、天然記念物を守るための大事な工程となっています。
愛好家からタマゴを預かり孵卵機(ふらんき)であたためられます。

孵卵機(ふらんき)
約3週間後、ヒナが誕生し育雛機(いくすうき)で育てられます。
このように、タマゴからったヒナの体調管理が難しい1か月の間、専用の機械で飼育されます。
ヒナは1か月後にもとの愛好家に返されます。
春にヒナがかえったら見に行こうと思います!
12月から翌3月の間は閉館となっていますのでご注意ください。
秋田三鶏記念館の基本情報
- 入館料:無料
- 開館時間:9:00~16:30
- 開館期間:4月~11月(冬期間は閉館)
- TEL:0186-43-7133
- 住所:〒017-0012 大館市釈迦内字獅子ヶ森1番地
- 休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)
まとめ
- 実物の比内鶏、声良鶏、金八鶏を見ることができる
- 4月から6月にかけてヒナを見ることができる
あわせてよみたい
山田定次氏についてはこちらをご覧ください。

|
|
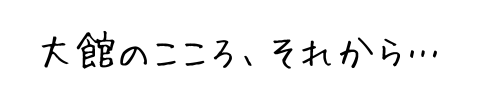

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3be27a85.66ab9cc2.3be27a86.d3977628/?me_id=1217311&item_id=10000036&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyoshi-ya%2Fcabinet%2F04772576%2F06636737%2Fod-02_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3be27a85.66ab9cc2.3be27a86.d3977628/?me_id=1217311&item_id=10000299&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyoshi-ya%2Fcabinet%2F04772576%2F06636737%2Fod-06_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

